一事不再理効とは
裁判が確定すると、以下の効力が生じます。
① 執行力:実体裁判の内容を執行することができる効力
② 拘束力:後続する同一当事者間で、裁判内容と矛盾する内容の主張・判断を禁止する効力
③ 一事不再理効
一事不再理効とは、有罪・無罪の実体判決、免訴判決の確定によって生じる、同一事件に対する再度の公訴提起を許さない効果のことです。
そのため、管轄違いの判決、公訴棄却判決には生じません。
337条1号は、「確定判決を経たとき」は免訴判決を言い渡さなければならないことを規定しています。このように、一度審判がなされた事件については、再びこれを審判の対象とすることが許されないことを、一事不再理といいます。
刑事訴訟法337条(免訴の判決)
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。
根拠
二重の危険の禁止(憲法39条)を根拠とするのが現在の通説です(二重の危険説。最判昭和25.9.27)。
二重の危険の禁止とは、同一の犯罪事実について有罪とされる危険(実体審理を受ける危険)に重ねてさらされることはないとする原則のことです(古江頼隆『事例演習刑事訴訟法(第2版)』440頁)。
憲法39条(遡及処罰の禁止・一事不再理)
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
一事不再理効の主観的範囲
二重の危険にさらされるのは手続の対象になった被告人のみであるため、一事不再理効は、訴追ないし判決を受けた被告人に対してのみ生じます。共犯者には及びません。
一事不再理効の発生時期
一事不再理効は裁判確定時に発生します(通説)。
一事不再理効の客観的範囲
上述のとおり、一事不再理効の根拠は、同一の犯罪事実について有罪とされる危険(実体審理を受ける危険)に重ねてさらされることはないという、二重の危険の禁止(憲法39条)にあります。
そして、訴因変更は「公訴事実の同一性」(312条1項)がある範囲で認められるため、検察官が訴因変更可能な範囲において被告人は有罪判決を受ける危険にさらされていたといえます。
したがって、一事不再理効は、訴因事実に限らず、確定判決に係る訴因との間で「公訴事実の同一性」が認められるすべての事実に及びます。
「公訴事実の同一性」は、訴因変更の場合と同様、①公訴事実の単一性と、②狭義の公訴事実の同一性に分けられています。
単一性の問題か狭義の同一性の問題かは、事案によります。
新訴因が犯罪として旧訴因と両立し得るものとして主張される場合⇒「単一性」
新訴因が犯罪として旧訴因と両立しないものとして主張される場合⇒「同一性」
公訴事実の単一性の判断方法
公訴事実の単一性は、実体法上の罪数を基準に判断します。実体法上一罪であるときは、単一性が肯定されます。
Q.確定判決を経た事件(前訴)の訴因と確定判決後に起訴された確定判決前の行為に関する事件(後訴)の訴因との間に公訴事実の単一性があるかどうかを判断するにあたり、訴因基準説を採るべきでしょうか、それとも、心証基準説を採るべきでしょうか。(ex.前訴が単純窃盗、後訴が常習特殊窃盗で、両者が常習特殊窃盗の包括一罪を構成する場合に、前訴の一事不再理効が後訴に及ぶか)
訴因基準説
実体法上の一罪関係にあるかどうかを、両訴因に記載された事実のみを基準にして判断する。
心証基準説
訴因外の事実について証拠によって心証形成して、実体法上の一罪関係にあるかを判断する。
原則
前訴の訴因と後訴の訴因との間の公訴事実の単一性についての判断は、基本的には、前訴及び後訴の各訴因のみを基準にします。
①訴因制度を採用した現行刑訴法の下においては、少なくとも第1次的には訴因が審判対象である(審判対象論)
②犯罪の証明がないとする無罪の確定判決も一事不再理効を有する
③一罪を構成する行為の一部起訴も適法になし得る(検察官の訴追裁量)
例外
もっとも、両訴因の記載の比較のみからでも、両訴因の両罪が実体的には一罪ではないかと強く疑われるときは、訴因自体において実体的には一罪を構成するかどうかを検討すべき契機が存在するため、訴因外の事実を考慮し(ex.単純窃盗罪が常習性の発露として行われたか否かについて)付随的に心証形成をし、両訴因間の公訴事実の単一性を判断します(やわらかい訴因基準説)。
*この場合に訴因外の事実について踏み込む必要があるのは、当該犯罪の性質から、加重された法定刑の犯罪によって1回だけ処罰されるはずであったのに、別々に起訴されたときは両訴因が併合罪関係となり、被告人にとって加重な結果をもたらすという不都合が生じるからです。
*[前訴:単純窃盗、後訴:常習特殊窃盗]の場合、一見すると前訴訴因が後訴訴因に包摂される関係にあるように思えます。しかし、常習性の発露としてではなく単純窃盗を行うこともあり得るため、当然に包摂されるわけではありません。単純窃盗が常習性等の各要件を満たして常習特殊窃盗罪に該当することを認定する必要があり、そのためには訴因外の事情を考慮する必要があります(調査官)。
最判平成15.10.7(百選10版97事件)は、「前訴の訴因と後訴の訴因との間の公訴事実の単一性についての判断は、基本的には、前訴及び後訴の各訴因のみを基準としてこれらを比較対照することにより行うのが相当である」としたうえで、「前訴及び後訴の訴因が共に単純窃盗罪であって、両訴因を通じて常習性の発露という面は全く訴因として訴訟手続に上程されておらず、両訴因の相互関係を検討するに当たり、常習性の発露という要素を考慮すべき契機は存在しないのであるから、ここに常習特殊窃盗罪による一罪という観点を持ち込むことは、相当ではない…。そうすると、別個の機会に犯された単純窃盗罪に係る両訴因が公訴事実の単一性を欠くことは明らかであるから、前訴の確定判決による一事不再理効は、後訴には及ばないものといわざるを得ない。」としました。
また、傍論で、「前訴の訴因が常習特殊窃盗罪又は常習累犯窃盗罪(以下、この両者を併せて「常習窃盗罪」という。)であり,後訴の訴因が余罪の単純窃盗罪である場合や、逆に、前訴の訴因は単純窃盗罪であるが、後訴の訴因が余罪の常習窃盗罪である場合には、両訴因の単純窃盗罪と常習窃盗罪とは一罪を構成するものではないけれども、両訴因の記載の比較のみからでも、両訴因の単純窃盗罪と常習窃盗罪が実体的には常習窃盗罪の一罪ではないかと強くうかがわれるのであるから、訴因自体において一方の単純窃盗罪が他方の常習窃盗罪と実体的に一罪を構成するかどうかにつき検討すべき契機が存在する場合であるとして、単純窃盗罪が常習性の発露として行われたか否かについて付随的に心証形成をし、両訴因間の公訴事実の単一性の有無を判断すべきである」としました。
客観的範囲の縮小
Q.「公訴事実の同一性」の範囲内の事実であっても、訴因変更が不可能な場合であれば、一事不再理効は及ばないのでしょうか。
【事例】
科刑上一罪の一部が親告罪で告訴がないため親告罪ではない部分についてのみ確定判決を受け、のちに告訴がなされた場合
一事不再理効が及びます。
これは、被告人から見れば、結果的に告訴が得られなかったことは検察官側の内部事情にすぎず、告訴がなされたうえで訴追されるという危険にはさらされていたといえるからです。
【事例】
傷害罪の判決が確定した後に被害者が死亡した場合のように、判決確定後に犯罪事実が変化した場合
一事不再理効が及ぶと解するのが通説です。
現行法では追加訴訟制度がないため、死亡結果を認定するためには傷害全体の審理をやり直さなければなりませんが、傷害全体の審理は一事不再理効によって許されません。傷害全体の審理が一事不再理効によって許されない以上、死亡結果についても一事不再理効が及び、再度の公訴提起は許されないと解すべきです(古江頼隆『事例演習刑事訴訟法(第2版)』444頁)。
【事例】
検察官において公訴事実が認められる他の罪をも探知して同一手続で追訴することが著しく困難であった場合
東京地判昭和49.4.2は、「一事不再理効は他の罪については及ばない」としました。
学説はこの昭和49年判決に批判的です。事実上困難であったかどうかを基準にすると、個別の事案ごとの判断になり、一事不再理効の及ぶ範囲が著しく不明確になるため、事実上困難か否かで客観的範囲を限定することは妥当ではありません。
客観的範囲の拡張
Q.「公訴事実の同一性」の範囲外の事実について一事不再理効が及ぶ場合があるのでしょうか。
同時訴追可能な事案(例えば、併合罪関係にある殺人罪とそれに用いた銃砲刀剣類の不法所持、過失運転致死傷と道路交通法違反(無免許運転や酒酔い運転))であれば、公訴事実の単一性がなくとも一事不再理効を及ぼしてもよいのではないかという見解があります(古江頼隆『事例演習刑事訴訟法(第2版)』445頁)。
しかし、客観的範囲の縮小の場合と同様、同時訴追可能かどうかを基準とすると、個別の事案ごとの判断になり、一事不再理効の及ぶ範囲が著しく不明確になるため、妥当ではありません。
一事不再理効の時間的範囲
Q.一事不再理効が発生しているとして、その効力はどの時点の行為にまで及ぶのでしょうか。公訴事実が同一ないし単一の事件が訴訟の前後にわたって行われた場合に問題になります(ex.常習犯、継続犯)。
(二重の危険説から)通説は、第1審判決言渡し時までは弁論再開の可能性があること、控訴申立理由として弁論終結後判決前に生じた事実を援用できることから、二重の危険にさらされるのは判決言渡しまでの行為であるとして、一事不再理効は第1審判決言渡し時までの行為にのみ及ぶと解します(第1審判決言渡時説)。
原則として第1審判決言渡時説を採り、控訴審裁判所が第1審判決を破棄し自判する場合には例外的に控訴審の判決言渡し時までの事実に一事不再理効が及ぶとする見解も有力です(リークエ2版497頁)。




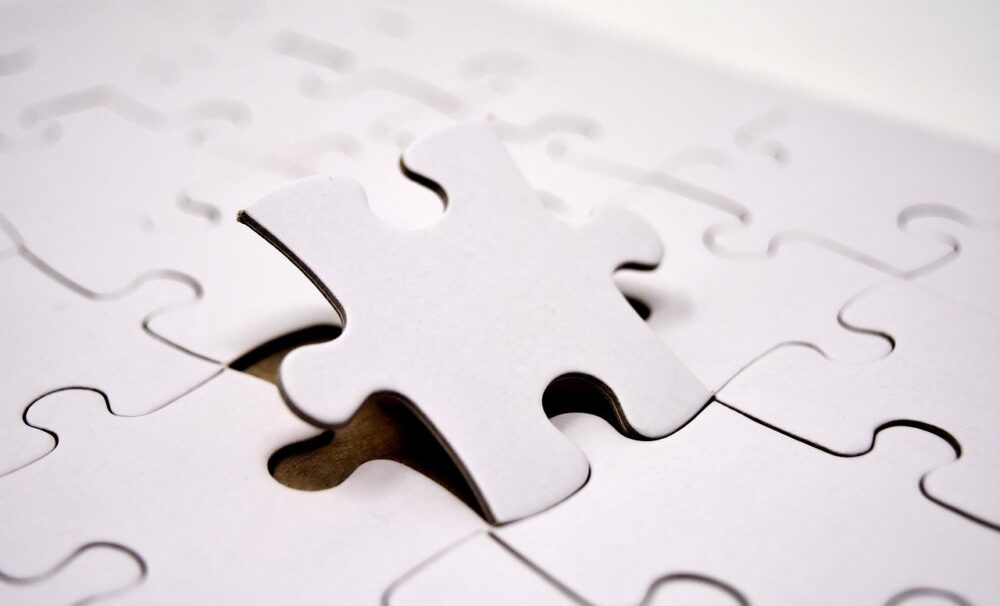
コメント